床下の断熱

初めにこの冒頭で言っておきますが「床断熱」は「基礎断熱」に比べて床は冷たいです。
今回はその両方の違いについてお話しします。
昔々、日本人は耐える人種と呼ばれていたようで寒いのは当たり前で厚着をするなりして我慢をして、それでもダメならストーブや薪を焚くという時代が長く続いていました。
徒然草に「家のつくりやうは、夏を旨とすべし」とあるように冬対策はされていませんでした。
床の下に断熱材を入れ始めたのは1980年ころからと言われています。
その後断熱の先進国であるドイツから基礎断熱の考え方が輸入され日本では北海道から使われ始めたと言われています。
今では本州はもちろん九州・沖縄でも基礎断熱で施工されています。
床断熱の施工方法
床材の裏側に断熱材を嵌め込む床断熱の方法は、初期のころからありました。
どういう施工かを説明しますね。
まず床の構造を説明します。
下から土台(大引)⇒根太(高さ45㎜or60㎜で約30㎝間隔)⇒捨貼り合板(厚さ12㎜)⇒床板、となっていて根太と根太の間、捨貼り合板の裏側に断熱材を敷き込む施工になります。
今では根太レス工法が多いと思いますが、根太の代わりに構造用合板(厚さ24㎜以上)が貼ってあり、この裏側に断熱材を敷き込む方法です。
この「床断熱のメリット」ですが…すみません、思いつきません><。
ネットではコストが安くなると出ていますが、実際に使う材料の必要最低限の面積は「基礎断熱」に比べて多いです。
では施工が簡単かと言われても、さほど技術も時間も変わりません。
強いて言えば、昔からある工法と最近の工法で、新しい施工方法は施工費が高くなりがち、ということくらいでしょうか。
床断熱が冷たい理由
冒頭に書いた「基礎断熱」と比べて床が冷たいというところですがそこが気になりますよね。
その理由をお話しします。
この場合の床下の空間温度は外気と同じです。
基礎換気口や通気パッキンで外気と床下の空気がいつでも入れ替わるようになっていて、その冬の冷気が断熱材以外の所から侵入するからです。
断熱材は根太と根太、あるいは土台と土台の間に施工しますので、冷気は根太があれば根太から、根太がなければ土台(大引)から直接室内に伝わってきて、床板に広がるのです。
外壁は日中は陽が当たるので断熱が無い柱や梁は多少熱を持ちますが、床下は外壁と違って日中も太陽の日が当たらなく根太や土台は冷たいままなので当然です。
そこで、冷たいなら温めれば良いと考える工務店・ハウスメーカーは「床暖房」を採用します。
床が冷たい理由がもう一つあります、それは気密が取れていないからです。
勝手に空気が入れ替わるからですね。
この二つが床を冷たくする理由で、逆に言うと断熱材を一面全体に施工してしっかりと気密を取る施工ができれば床は冷たくならないと言えます。
実際に施工も可能ですがそれこそコストアップになると思います。
床暖房は必要か
ここで少し脱線します。
「床暖房」のお話が出たので少しだけ詳しくご説明します。
エアコンのように風が出ないから好きという方もいらっしゃると思います。
「床暖房システム」は熱源に主に2通りの種類がありまして、1つ目の「温水式」は温水パイプをパネル化したもの、2つ目の「電気式」が電熱線(鉄線或いはカーボン粉末)をフィルムに挟んだシート状のものです。
6畳分を施工した場合、イニシャルコストは30万~60万円程でランニングコストは4000円~7000円/月でになります。
メンテナンスは温水パイプの方で必要で不凍液の交換やパイプ内の洗浄が10年ごとに数万円、熱源機(給湯器一体型)は10年~15年で交換になり30万~40万円ほどかかります。
LDKや洗面室、トイレにも施工するとなると、2倍~3倍費用がかかることになります。
しかも、熱源がある箇所しか温まりませんので、温度ムラは感じてしまいます。
ハウスメーカーでは、毎月のランニングコストがかかるので、その埋め合わせを太陽光で賄おうという考えが主流の様です。
万が一、貼替えとなると床板から再施工になるので、150万~数百万円になるでしょう。
基礎断熱のメリット
戻ってまいりました。
次は「基礎断熱のメリット」についてです。
ズバリ、「床が冷たくならない」です。
その理由は床下の空間が外気とは隔離され部屋の中とほぼ同じ温度が保てるからです。
基礎断熱には施工する箇所によって3種類に分けられます。
外周の基礎の立上りに施工するのは同じですが、断熱を貼る場所によって内断熱、外断熱、その両方の3種類です。
断熱で考えると外側に施工する方が理に叶っていると思いますが、外断熱と内外両方に断熱する場合の注意点は、基礎と断熱材の間に侵入するシロアリの対策をしっかりと取らないといけけない点です。
外側の断熱材が蟻害を受けたり基礎の天端から中に侵入してくる事故もよくあるので要注意です。
次に内断熱ですが立上りと底板(ベース)にも敷設します。
最低60㎝の幅は必要で90㎝あると安心です。
冷気が基礎の立上がりの下から回り込んで内部まで入ってくるのをシャットアウトする為です。
そして細かい部分ですが3つの方法でいえることで、基礎の上にある土台からも冷気が伝わりますので、基礎の立上がりから連続して土台の天端まで断熱材を施工するのが良いと思います。
基礎断熱の注意点
もちろん良いことばかりではありません。
先ほど床断熱は気密が悪いから床が冷たいと言いましたが、基礎断熱は気密を取りやすいのがメリットになります。
そしてこのメリットがデメリットを引き起こす原因になるのです。
空気の出入りがないために温度の移動も起こらないのですが、同時に湿気も動かないので強制的に換気をしなければなりません。
基礎の成分は、セメント・砂・砂利、そして水です。
セメントが水と反応して硬化し固まるのですが、水分は1~2年間は基礎から放出し続けます。
その水分の逃げ場所がないと、床下がジメジメしてカビや腐朽菌でいっぱいになってしまいます。
基礎の内部には構造上必要な立上りがあるので区画されてしまい、思ったより床下の空気は動きませんから床下の換気対策は十分に確認することをお勧めします。
初めての家づくりのために勉強会を開催しています
「いつかマイホームを…」そう考えているあなたへ。夢の実現に向けて、まずは情報収集から始めてみませんか?
夢工房キッチンくらぶでは、これから家づくりを始める方を対象に「家づくり勉強会」を定期的に開催しています。家づくりの基礎知識から、資金計画、土地探し、間取りの決め方まで、プロがわかりやすく解説します。

個別での質疑も可能ですので疑問点をその場で解決できます。理想の住まいを実現するために、一緒に学び、夢を形にしていきましょう。
夢工房キッチンくらぶは名古屋市を中心に、日進市、尾張旭市、春日井市、長久手市、瀬戸市、あま市、小牧市、稲沢市、一宮市、東郷町、みよし市、海部郡飛島村、知多郡阿久比町、半田市、津島市、大府市など愛知県で注文住宅、新築一戸建ての設計・施工を手掛けています。お気軽にご相談ください。
この記事の執筆者

小浦義一 こうらよしいち
Website
名古屋市の建築会社 夢工房キッチンくらぶ代表 1971年生まれ。
大工にてキャリアをスタートし大手ハウスメーカー設計の住宅を数多く手掛ける。
図面に忠実に、そして技術的に無駄が無い。ことを心情とし建築家設計の難解な住宅の施工も担う。手掛けた案件が新建築に掲載された実績もあり。
会社設立後は全てのお客様の図面、線一本にも責任を持つことを掲げ、一棟一棟、熟練の職人とともに年間受注棟数を限定しながら、高断熱・高気密・高耐震、そして自然素材を主とした健康で安心して永く住み続けられる住みやすい住宅を提供している。
主な資格は、二級建築士、住宅断熱アドバイザー、住宅断熱施工技術者、第二種電気工事士 宅地建物取引士 など
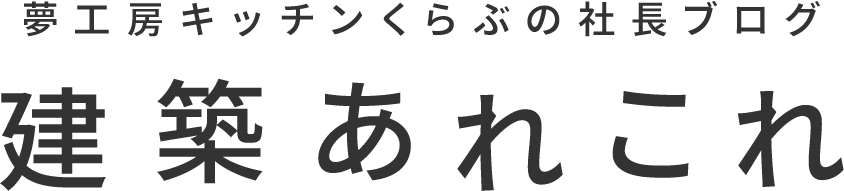



コメント